- 2021年8月31日
- 256 view
「自分のやりたいことが分からなくなった」と悩むあなたが疑うべき、2つの着眼点。
この記事では、自分のやりたいことが分からなくなったときに着目すべき2つのポイントを解説します。 この……
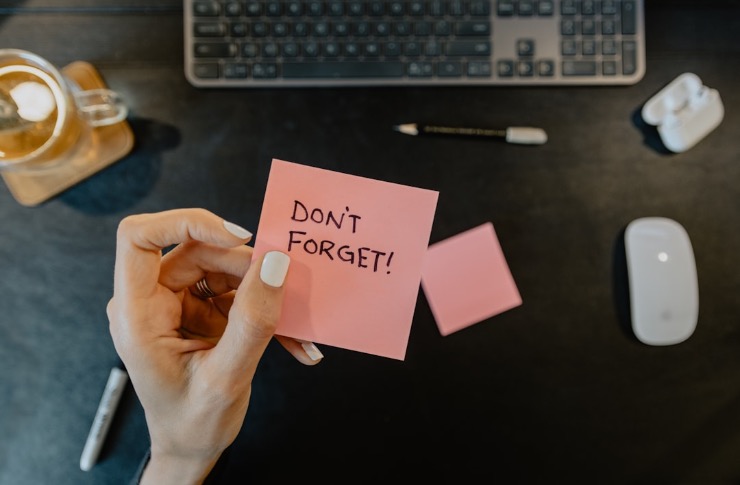

「また忘れちゃった…」そんな自分に、ガッカリしたことはありませんか?
「どうして自分はいつもこうなんだろう」「周りはちゃんとしているのに」
そうやって“できない自分”を責めてしまうこと、ありますよね。
でも実は──その「忘れっぽさ」や「うっかり」は、欠点ではなく“才能の種”かもしれません。
今回は、ぼく自身のちょっと笑える「忘れっぽい話」を通して、あなたの中に眠る“強みの見つけ方”をお伝えします。
突然ですが、質問です。
あなたは、周りから自分のことをどんな人だと思われていますか?
周りの人は、ぼくのことをこう言います。
「元刑事だから、きっとしっかりしている人」って。
でも実は──ぼく、けっこう忘れっぽいんです。笑
同じ食材や調味料を何度も買ってしまったり。
財布を持っていないのにコインパーキングに入ったり。
しかも駐車場所の数字を間違えて、他人の駐車料金を払ってしまったこともあります。
もう、我ながら“ボケっぷり”がすごい。笑

小学生のとき、とにかく忘れ物が激しく多い子どもでしたw
「また忘れた!」「もう、さっきまでは覚えてたのに!」そんな日々が続き、ついに小学生のときに決意したんです。

「もう、自分を信用しない。」笑
そこから毎晩、前日に持ち物を準備。朝はテレビを見ずに再チェック。
──結果、忘れ物ゼロ!!(感動)
さらに「忘れたくない」という思いが強くなり、小さなメモ帳を持ち歩いて、何でも書くようになりました。
・どうすれば覚えやすいか?
・どうすればメモを使いやすくできるか?
そう考えるうちに、自然と“工夫する力”や“仕組み化の発想”が身につきました。
いまでもぼくは、自分をあまり信用していません。笑
すぐにサボるし、怠けるし、忘れる。
だから、思いついたことはすぐメモ。やることは全部リマインダー登録。
未来の自分に「あとで思い出してね」と通知を送る日々です。

ある日、ふと思いました。
「忘れっぽい自分を責めてきたけど、 “忘れないように工夫する力”は、ぼくの強みだったのかもしれない。」
そう気づいたとき、ひとつのことがわかったんです。
人にはそれぞれ、人生でずっと自分に問いかけてきた言葉があります。
才能のヒントは「人生で何を問い続けてきたか」
たとえば、ぼくの場合──
気がつけば、ずっと自分に問いかけている。何年も、何十年も考えてきました。
その結果、メモを取る習慣や仕組みづくり、改善思考が身につきました。
つまり──
忘れっぽいという“欠点”は、ぼくの“才能”を育ててくれた土台だったんです。
そして問いこそ、あなたの才能を育ててきた種なんです。
才能や強みとは、生まれつきのセンスではなく、
「そこにどれだけの時間を使ってきたか」で見えてきます。

人は、苦手を克服しようとしているときこそ、誰よりもそこに時間とエネルギーを注ぎます。
だからこそ、「どんな問いをしてきたか?」を思い出してみてください。
もしそんな問いを繰り返してきたあなたは、きっと“自信を与える人”だったり、“人間関係を育てる人”だったり、はたまた“継続できる人”として、すでに周りを支えているはずです。
「忘れっぽい自分」も「不器用な自分」も、見方を変えれば、誰かを助ける“強み”に変わります。
大切なのは、欠点を責めることではなく、その中にある”工夫・問い・時間”を見つめること。
あなたがこれまでずっと自分に問いかけてきた言葉。
その中に、あなたの才能の原石が眠っています。
ぜひ、思い出してみてください。
それは、世界であなただけが持っている“強み”の証です。
