- 2026年1月30日
- 15 view
人は、自分が「分かっていること」ほど言葉に出る|元刑事が見てきた無意識の正体
人は、自分が「分かっていること」ほど言葉に無意識が出ます。 これは、刑事として何千人もの話を聞……
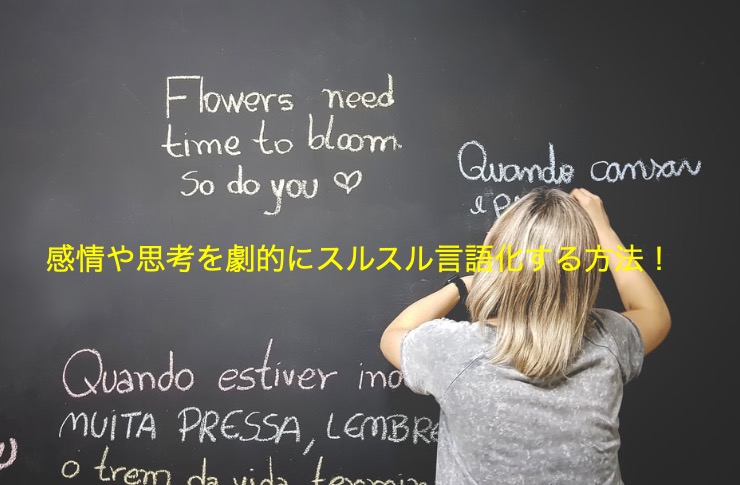
この記事では、気持ちや思い、考えを言葉にする”言語化”ニガテ女子のために具体的な思考の見える化や自分の感情を言葉にするためのコツをお伝えします。
この記事を読むことで今まで言葉にならない気持ちや思い、感情を抱えていたあなたも少しづつ言葉にして、人に伝えることができるようになりますのでぜひ参考にしてみてください。
まず、言語化できることのメリットは大きくわけて次の3つに集約されます。
①自分が本当に伝えたいことが相手に伝わる
②思考が整理できる(要約力が身に付く)
③自分自身を客観的に見ることができる
1つずつ詳しく解説していきます。
人間は言葉を使って相手との意思疎通を図ります。言葉は話すだけではただの自己満足です。
「伝えること」と「伝わること」は似ていますが、まったく違います。
言語化が得意な人は相手に「伝わる」コトバを使っています。
コミュニケーションにおいて相手に伝わることがもっとも大切なことはあなたもわかっているはず。
伝わったかどうかは常に相手が判断します。
伝言ゲームのように最初に伝えた言葉と最後に伝わった言葉が違う場合には”伝わる”とはいいません。
だから自分が考えていること、伝えたいことをハッキリ言葉として表現することで、相手に自分の意図がちゃんと伝わります。
「伝えたいことはっきり言葉にして伝わる=言語化」ができる人はビジネスやプライベートにおいて、自分の伝えたいメッセージや考えが正確に伝わるので上司や取引先、家族に対して自分の意見や提案が通る可能性が高まります。
また、言語化が得意な人は「わたしの伝えたいことと違う・・・」自分の考えとは違うメッセージが相手に伝わってしまう失敗を避けることもできます。
『9割捨てて10倍伝わる「要約力」/山口拓朗』のなかで、要約力とは『情報のポイントをつかみ、場面に応じて、簡潔かつ論理的にアウトプットする能力のこと』と解説しています。
言語化が得意な人は、思考の整理が得意な人です。今までに「見た」「聞いた」「体験した」インプット情報を整理して、相手に必要な情報だけをアウトプットすることができます。
相手にとって必要な情報を、伝わる言葉でアウトプットすることができるので、相手の時間を奪うことなく、短時間で相手に伝えることができます。つまり、仕事の生産性や効率化につなげることができます。
言語化能力が高まると、いらない情報をどんどん捨てて、本当に伝えたいメッセージのコアだけを高めていくことができます。山口さんの本は、とってもいい本なので言語化をさらに高めたい人にはおすすめです。
言語化が得意な人はセルフコントロールやセルフコーチングができます。
なぜなら、自分の思考や感情を客観的に振り返って、言葉として書き出すことができるからです。
自分の思考や感情を客観的に振り返って言葉にできる人は、自分のカラダや感情の変化にすぐ気づくので極端な感情の上げ下げが少ないのです。

つぎに言語化できないデメリットですが、大きく分けて次の3つがあると思います。
言語化が苦手な人は自分の言いたいことだけを話して、相手に真意が伝わっていないということが多々あります。
相手に真意が伝わらないことで自分の思いとは違う方向に物事が進んでしまったり、上司やお客様、クライアントさまとトラブルに発展する危険があります。

また、言語化が苦手な人は話がダラダラと長くなってしまうことが多々あります。
短い言葉だけでは自分のメッセージが伝わらないかもしれない。だから、どうしても1から10まで説明したくなってしまうのです。
そこには自分が言っていることは伝わらないかもしれないという「自信のなさ」(マインド)が隠れている可能性もあります。
言語化が苦手な人は客観的に自分を表現することがむずかしいので「自分紹介」がニガテな場合も多いです。
「わたしは〇〇で、〇〇していて、〇〇もしていて、こうなんです、こうなんです・・・」なにを伝えればいいかわからないから、とにかく盛り込んでしまい、結局なにが言いたいのか、わからなくなってしまうパターンに陥ることがあります。
では、なぜ言語化が苦手になってしまうのでしょう?次に解説していきます。
ひとつ、ひとつ詳しく解説します。
言語化が苦手な人はとにかく「アウトプット(書く・話す)」をしていないケースが多く見受けられます。
そのため「これはこうだから」「あれはこうだから」と頭のなかで考えて、自己完結して言葉を脳から出さないので、言語化するスキルが磨かれないのです。
言語化が苦手な人は「インプットが少ない方」が多いです。見る・聞く・体験するというインプットが少ないと脳は刺激を受けないので、アウトプットもなくなるという悪循環になります。
後述しますが、とくに言語化の塊である「読書」というインプットが少ないと自分のなかにある語彙力も増えていきません。言語化苦手な人にとって、読書はとても大切なことです。
言語化が苦手な人は「物事をおおざっぱに捉えている方」が多いです。専門用語で抽象化ともいいますが、わかりやすく言うと「桜」や「たんぽぽ」を見ても「花」とひとくくりにしたり、「象」や「ライオン」を見ても「動物」とひとくくりにするような感じです。
身体の調子が悪い場合も「なんか調子悪い」と言って、「頭が痛いのか」「お腹が痛いのか」物事を細かく捉えて表現することが少ない傾向にあるので、言語化スキルを高めることができません。
言語化が苦手な人は「脳のなかにある語彙力が足りない」という点があったりします。
語彙力が足りないと、普段からなにをしても「ヤバい」「すごい」「うま」「はや」などと省略した言葉や俗語を連発するようになります。そして結果的に、言語力を磨くことができません。
ちなみに、やばいの語源は明治時代にあるって、知ってましたか?
日本語どうでしょう?「やばい」の新しい意味明治時代の隠語辞典を見ると『てきや・盗人などが官憲のことを「やば」』と呼んでいたらしく、また、そのような世界の人が官憲などの追及がきびしくて身辺が危ういときにも「やばい」と言っていたらしい。
言語化が苦手な人は「どうせ私は言語化が苦手だから」という苦手意識(口ぐせ)を持っているケースが多いです。事実かもしれませんが、言語化はトレーニングでいくらでも磨くことができます。
まずは苦手意識があってもいいから「わたしにもできる」と決意することが大切です。
また、苦手意識を持ってしまったのにはきっかけがあるかもしれません。親や先生から言われた、クラスメイトから馬鹿にされた、読書感想文が苦手だったなど、ほんとうは言語化が得意な可能性もあります。
自分の可能性を自分で閉じることを選択せずに、数をこなすことで必ず言語化はできるようになります。

この記事を書くにあたって、いろんな情報を検索しました。そのなかでHSP(繊細さん)は言語化が苦手という記事をいくつか見ました。
たしかに繊細さんは自分の考えや気持ちを人に伝えるのが苦手だと思います。ただ、言語化が苦手だとはぼくは思いません。繊細さんはその気質ゆえに自分のカラダの変化や環境の変化に敏感です。
その変化を自分のなかで細かく言語化するのは得意なはずです。それを人に伝えたり、理解してもらうのが苦手なんだと思うんです。つまり、言語化が苦手なのではなく、コミュニケーションが苦手なんです。
というのもぼくはHSP・エンパス体質です。コミュニケーションは苦手ですが、言語化は得意です。
言語化が得意なことに気づいたのは「高校時代」です。今まで論文や感想文を書くのが苦手だと思って、避けてきたのですが、大学受験のためにどうしても書かなければいけなくなり、とにかく数をこなすと短時間であっという間に書くことができたのです。
なんだ、文章にするのって意外に簡単なんだなと思ったのをいまでも覚えています。
いまは対人サポートで女性とオンラインやリアルでお仕事させていただく機会が多いのですが、「あーそれが言いたかったんです」「わたしの言いたいことをまさに言ってくれました!」と言語化についてありがたい言葉をたくさんいただきます。
また、こうしてブログを書けているのも、20代から5,000冊以上の本を読み、刑事時代に何千という報告書を作成して上司に数えきれないほど書類を直されながら、言語化のトレーニングをさせてもらったからだと思っています。
だからとにかく数をこなすことで誰でも言語化することはできるようになるとぼくは信じています。ということで、次は言語化苦手さんがどうすれば言語化できるようになるのか?具体的な方法をお伝えします。
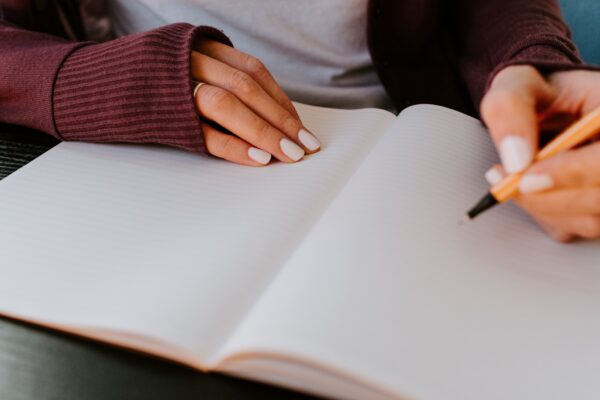
言語化するために次の3つがオススメです。
まずは読書をしてインプットを増やすことが言語化に向けたスタートです。「言葉のインプットが少ない=それだけ自分の中に言葉のストックが少なくなる」ということです。
読書をすることで「作者(他人)の考え方」「言葉の使い方」「語彙力」などを総合的に磨くことができます。
脳に言葉がどんどんストックされていきます。ストックが多くなれば、自分が言葉をアウトプットするときに使える言葉も増えるということです。
読書が苦手な人は「金言集」「名言集」「好きな芸能人や有名人のエッセイ」などページごとに内容が完結している本を選ぶとよいです。
これなら読めそうだなという薄い本でOKです。どうしても読むのが苦手という人は「オーディオブック」などの音声でもいいと思います。

そして、大切なのは読みながら考えるということ。
「なんで作者はこの言葉を使ったんだろう?」「その背景にはどんなことがあるんだろう?」「自分ならこの状況でどんな言葉をつかうだろう?」考えることで思考が鍛えられ、考えれば考えるほど言語化も磨かれていきます。
具体的にどんな本を読んだらいいんだろう?と思った方は下記記事を参考になさってください👇
思考することも大事ですが、もっと大事なのはアウトプットすること。「実際に言葉にして使ってみる、文章にしてみること、人に話すこと」で言語化はどんどん磨かれていきます。
アウトプットとは「紙などに書き出す」「人に話す」「SNSやブログに発信する」こと。
元マイクロソフト代表取締役の成毛眞さんは著書「黄金のアウトプット術 インプットした情報を「お金」に変える」でこんな話をしています。
黄金のアウトプット術 インプットした情報を「お金」に変える日本の大人にはアウトプットが不足している。しているのはインプットばかりだ。職場など周りを見渡しても、目につくのはインプットには興味津々、熱心な一方で、アウトプットが足りていない人間ばかりなのではないだろうか。アウトプットが不足している人間は、魅力がない。何を考えているかがわからない。
紙に書き出したり、人に話したり、SNSやブログに発信しようとすると、いっきに緊張感が高まりますよね!
「なにを書き出せばいいだろう?」「どんな言葉を伝えればいいんだろう?」「どうしたら相手に自分の思いが伝わるだろう?」「どうしたら本の内容が伝わるだろう?」「もし馬鹿にされたらどうしよう?」
その不安はよくわかります。全く伝わらなくて、失敗して、凹んでもう二度とやらない。そう思うかもしれません。でもその不安や失敗が言語化を磨くエネルギーになります。
「そうか、こうすれば伝わるのか!」相手の伝わったときの嬉しさはなにものにも変え難いもの。諦めずにトライ&エラー、PDCAサイクルを回すことであなたの言語化はどんどん磨かれていきます。
ちなみに人に伝える言語化のときは「5W1HプラスO」を意識するといいです。
When(いつ)、Where(どこで)、Who(誰が・を)、What(何が・を)、Why(なぜ)、How(どのように)、Outcome(結果)のこと。
ぼくも刑事時代は上司に報告するときはこれをつねに意識していたし、報告書も作っていました。
文章を作るときは「PASONAの法則」を意識するといいです。
Problem(問題): 顧客が抱えている悩みや課題を明確にする。
Agitation(煽り・問題の深堀り): 問題が解決しないとどうなるか、危険性を伝えて意識させる。
※近年では『Affinity(親近感・共感): 顧客の悩みに共感し、信頼を得る』が使われることも多い。
Solution(解決策): 問題の解決策となる自社商品・サービスを提示する。
Narrow down(絞り込み): ターゲットや期間、数量を限定し、いま購入すべき理由を作る。
Action(行動): 購入、問い合わせなどの具体的な行動を促す
ググると詳しい解説がたくさん出てくるのでここでは解説を省きます。
「人に話したり、SNSやブログでアウトプットするのは、ちょっと…」という人は本を読んだ感想や感じたことなどを、ノートに書いたり、スマホにまとめてみることからやりましょう。
日記を書くことのメリットは2つあります。
1つ目は、日記を書くことによって日々の微かな自分の感情や思考の変化を客観的に知ることができるようになります。
2つ目は、自分の感情や思考の変化に素早く気づくことができる(感覚が鋭くなる)ようになります。
多くの人は、「嬉しい」「悲しい」などの感情をひとくくりに考えてしまう傾向があります。
だから「どんなふうに嬉しかった?」「なにが嬉しかった?」など意図的にその感情をこまかく細分化して言葉にすることで言語化を磨くことができるようになります。
また日記を書くからという意識があるので、そのネタを探そうと脳の回路も変わって、一つひとつの行動に対するアンテナが鋭くなります。
日記は1日の最後に書くのでどんなことがあったか忘れやすいという人は、その都度スマホにパパッとメモするのもいいです。最初は日記になにを書いたらいいかわからないと思うので、簡単に書ける「3行日記」がオススメです。
順天堂大学医学部教授小林弘幸さんの著書「3行日記」を書くと、なぜ健康になれるのか?」で
「3行日記」を書くと、なぜ健康になれるのか?「3行日記」とは、寝る前に「①今日一番失敗したこと」「②今日一番感動したこと」「③明日の目標」それぞれを1行ずつ書くことと解説しています。
日記って正直めんどくさいと思うんです。人が習慣化するまでには「20日」くらいが必要って言われています。だから習慣化を目標に、どれか一つだけでもOKなので小さく始めてください。
また、精神科医の樺沢紫苑さんの著書「精神科医が見つけた 3つの幸福」の中で解説している「3行ポジティブ日記」もオススメです。
これは寝る前に1日にあった「嬉しかったこと」「楽しかったこと」などポジティブなことを3つ書くというもの。
ポジティブ日記のいいところは幸せホルモン(セロトニン)が分泌されて、幸せで感謝にあふれた状態で眠りにつくことができるということです。幸せな気持ちになれて、言語化も磨ける・・・最高ですよね!
紹介した2つの日記の書き方を参考に、やってみようかなと思えた方をトライしてみてください。もちろん普通の日記でも大丈夫ですよ。まずは小さく始めてください。
ぼくはiPadとApple Pencil(「A journal」というアプリを使っています。自分で使いやすいようにテンプレートを作って、カスタマイズすることができる。色んな手帳アプリを使った中でもダントツにいい)で1日の振り返りをしています。
純正メモや手帳アプリに書きますが、デジタルを使うと写真なども簡単に貼り付けることができるので絵日記みたいで楽しいですよ!
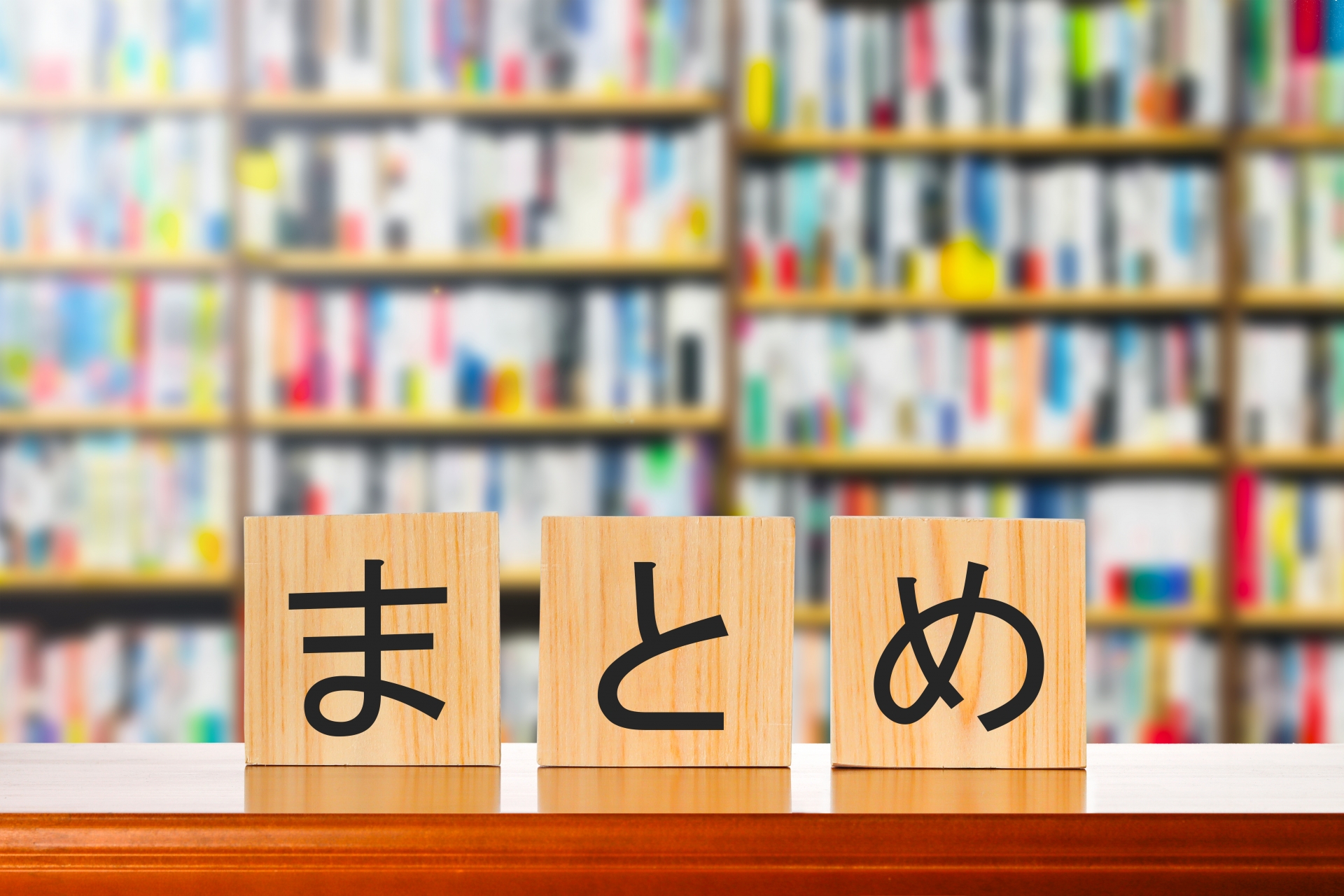
この記事では言語化が苦手な女性のために言語化のメリット・デメリット、言語化が苦手になってしまう原因、言語化を磨くための具体的な方法についてくわしく解説しました。
言語化できるようになることで本文でもくわしく解説したように
など多くのメリットがあります。
「わたし言語化苦手なんです」まずはその口ぐせから意識してやめていきましょう。「いまは”まだ”言語化が苦手なだけです」人には可能性しかありません。あなたには伸びしろしかありません。
できることから小さく始めることで、いつの間にか言語化が磨かれて、自分の伝えたいメッセージが相手に正確に伝わるようになります。
読書するといってもどんな本を読んだらいいの?そんなあなたのために言語化スキルを高める書籍10選をこちらに紹介していますので、ぜひ読んでみてください!